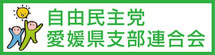〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

議会報告
令和7年2月28日(金)№1 代表質問 鈴木議員(自民)
1 地方創生の実現に向け、人口減少対策を今後どのように展開していくのか。
石破総理は今国会の施政方針演説で、自らの政策の核心に地方創生2.0を据え、「令和の日本列島改造」として、強力に進めていく決意を述べた。
「地方こそ成長の主役」という総理の考えに基づく地方創生2.0は、昨年末に基本的な考え方が示され、今夏には、基本構想が取りまとめられるとのことであるが、基本構想の策定に当たり設置された新しい地方経済・生活環境創生会議の有識者委員に、都道府県知事を代表する立場として中村知事が選任され、自治体トップとしての豊富な経験に裏打ちされた俯瞰的、建設的、具体的な提言を打ち出しているほか、今月22日には、本県で第4回会議が開催され、関係者とともに県内の地域資源を活用した地方創生の取組みを発信するなど、存在感を示している。
地方創生2.0の基本的な考え方では、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていくため、東京圏への過度な一極集中の是正、若者や女性にも選ばれる地方をつくることなどがうたわれているが、本県では、既に、デジタル技術を駆使した移住促進や仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進など、国に先駆けて各般にわたる対策を講じている。
しかし、先月末に国が公表した令和6年住民基本台帳人口移動報告では、本県の転出超過数は4,444人と前年よりも拡大し、そのほとんどを15~29歳の若者が占めているほか、昨年の出生数についても前年を下回る水準で推移するなど、少子化や社会減の流れを変えるまでには至っておらず、この問題の難しさを改めて痛感している。
人口減少対策は一朝一夕で成果が表れるものではないが、コロナ禍で縮小しつつあった転出超過数が、若年層を中心に再び拡大傾向にある中、地方創生を実現していくために、引き続き、粘り強く取り組む必要がある。
2 「こどもまんなか社会」の実現に向け、今後どのように取り組んでいくのか。
国が公表した人口動態統計の速報値を基にした試算では、令和6年における全国の日本人の出生数は、初めて70万人を下回ることが見込まれている。国立社会保障・人口問題研究所が一昨年に公表した将来推計では、6年の出生数は75万5,000人で、70万人を下回るのは20年と見込まれていたことから、想定を上回るペースで少子化が進んでいる。このような少子化や核家族化の進行により、地域のつながりの希薄化が加速し、子どもや子育てを取り巻く環境が大きく変わってしまうのではないかと危惧している。
全ての子どもの権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を掲げた、こども基本法が施行されてまもなく2年を迎える。家族の在り方や家族を取り巻く環境が変化し、多様な選択肢がある中、自らの主体的な選択により、子どもを生み育てたいと希望する若者に対しては、当事者目線での結婚や子育て支援などを進めていくことが必要である。さらには、性別や年齢にかかわらず、誰もが多様な生き方を選択できるよう、個人や職場における固定的性別役割分担意識の解消を始め、社会や個人の価値観の変容に合わせた環境づくりも不可欠である。
このような中、県は、「こどもまんなか社会」の実現に向け、今後5年間の子ども施策の方針である県こども計画の策定を進めている。子どもや子育てを取り巻く環境は絶えず変化していることから、計画策定後も、引き続き、子どもや子育て当事者に寄り添った実効性のある取組みを期待する。
3 官民共創拠点の開設に向けて、今後どのように取り組んでいくのか。
来年4月の供用開始を目指し、現在、新第二別館の建設が進められている。今回の整備の特徴の一つが、1、2階に整備する官民共創拠点であり、昨年9月定例会において、知事から「県内市町を始め企業やNPO、大学など幅広い関係者が多様な知見やノウハウ等を持ち寄り、対話を重ねながら一緒になって地域課題の解決や、革新的で実効性のある新規プロジェクトの創出に取り組む施設にしたい」との答弁があった。時宜を得たものであり、県民の一人として、完成を心待ちにしている。
また、今国会の石破総理の施政方針演説では、地方創生に約3割の分量が割かれ、官民が連携して地域の拠点をつくり、地域の持つ潜在力を最大限引き出し、ハードだけではないソフトの魅力で人の流れを生み出すとともに、新技術を徹底的に活用し、一極集中を是正し、多極分散型の多様な経済社会を構築していくと述べるなど、国の地方創生への取組みは、官民共創拠点の整備を進める本県にとっても強力な追い風になるものと感じる。
県では、これまでも人口減少に伴う国内市場の縮小を見据え、農林水産物を始めとした本県の優れた食品や、スゴ技などの県内企業の高い技術力に裏付けられた製品の販路拡大を図る「愛のくに えひめ営業本部」の取組みや、デジタル技術を様々な産業の現場等に実装し、県内事業者の稼ぐ力の強化や生産性の向上等を目指すトライアングルエヒメを始め、県内4大学と連携したデジタル人材の確保やスタートアップの創出など、新たな施策に矢継ぎ早に取り組み、成果を上げている。
しかし、全国の自治体が地方創生に注力する中で、官民共創拠点を成功に導くには、県内外の様々な事業者が集い交流しやすい魅力ある施設整備や、数多くの共創が生まれる運営面での工夫も重要と考える。
4 Velo-city2027の誘致の意義をどのように捉え、開催に向けどう取り組んでいくのか。
県は、自転車新文化の推進を主要施策の一つに掲げ、サイクリングを切り口とした交流人口の拡大や地域活性化に段階的かつ戦略的に取り組んできた。 中でも、しまなみ海道は、地域を代表する国際イベントとして定着したサイクリングしまなみの開催や国内外への強力なプロモーションにより、CNNの世界7大サイクリングルートや国のナショナルサイクルルートに選定されるなど、サイクリスト憧れのエリアへと成長し、近年は外国人が自転車でしまなみ海道を走行する姿が多く見られるなど、正にサイクリストの聖地の名にふさわしい地位を確立している。
さらに、しまなみ海道だけでなく、ブルーラインの整備等により県内全域にサイクリングコースを設定するとともに、シェア・ザ・ロードやヘルメット着用の啓発など自転車の安全利用を図ることで、誰もがサイクリングを楽しめる地域づくりを推進するなど、着実に成果を上げている。
このような中、県では、これまでの自転車施策を国内外に発信し、国際的な認知度をより一層高めるため、世界最大級の自転車国際会議「Velo-city」の誘致に取り組み、先日、令和9年の開催地に決定したと発表があった。知事のリーダーシップの下、関係者が一丸となってこれまで育んできた自転車新文化の取組みが世界に認められたものであり、誇らしく思う。
同会議は1,000人を超える自転車関係者が集まり、自転車の安全利用を始め、都市計画や観光面での活用など様々な議題について議論するとともに、県民参加型イベントも予定されているとのことである。Velo-cityの開催により、欧州を中心としたサイクリングが盛んな地域などでの本県の知名度が向上し、今後更に多くのサイクリストが本県を訪れ、地域活性化につながることを期待する。
5 インド経済交流ミッションの成果はどうか。また、ものづくり企業の海外展開支援に今後どのように取り組んでいくのか。
知事は、今月2~7日に県内経済団体等と連携し、2年連続、2回目となるインド経済交流ミッションを実施し、総勢80人の大規模な訪問団とともに、インド南部のタミルナドゥ州を訪問し、県内企業と現地企業との商談会の開催や、現地大学等と連携したインド人材の誘致促進などに取り組んだ。
昨年11月末にジェトロが公表した海外進出日系企業実態調査でも、今後1~2年の事業展開の方向性について、インド進出企業の8割以上が「拡大」と回答するなど、成長を続ける巨大市場への期待は、更に高まると思う。
一方、現時点では、インドでビジネスを行う日系企業は、大企業が中心となっている。今後の国内市場の縮小や労働力人口の減少等を見据え、将来的に、インドとの経済交流を本県経済の活性化に結び付けるためには、幅広い県内企業の現地でのビジネス機会の創出や人材確保に向けた取組みを後押しし、交流の裾野を広げていくことが重要である。
県では、前回の経済交流ミッションで構築した現地政府とのLocal to Localの交流基盤や、信頼できるビジネスパートナーとの人脈を礎に、現地に精通するアドバイザーやサポートデスクの設置など、ビジネス環境等が厳しいとされるインドならではの支援体制も構築しながら、県内企業のリスク低減や不安の解消を図りつつ、機動的できめ細かなサポートを通じて、インドとの経済交流を進めてきた。さらに、先日のミッションでは、県産水産物の輸出など、新たな試みにも果敢に挑戦しながら、県内企業のビジネス機会の創出と人材確保に向けた取組みを強力に推し進めた。
県として初の2年連続でのミッション実施など中長期的展望を持ちながら、一気呵成にインドとの交流を進める知事のリーダーシップと卓越した戦略眼に敬意を表するとともに、将来、取組みが実を結ぶことを期待する。
6 紅プリンセスの生産・販売に今後どのように取り組んでいくのか。
県オリジナル品種の紅まどんなを始めとする高級中晩柑は、品質の高さから市場や消費者からの信頼が厚く、販売シーズンの引き合いは旺盛と聞いており、温州みかんの収穫が終わる頃から、時期をずらしながら旬を迎える紅まどんな、甘平、せとかなどのリレー出荷は、他の産地では決して真似のできない本県の強みである。
このような中、期待の新品種である紅プリンセスの本格販売が開始される。紅プリンセスは、紅まどんなと甘平を掛け合わせ、紅まどんなのゼリーのような食感と甘平の濃厚な甘さを併せ持つ、正に柑橘界のサラブレッドである。
また、西日本豪雨において、県みかん研究所の試験園地の紅プリンセスの苗木が奇跡的に被災を免れ、このことが、被災農家の経営再開に向けての心のよりどころになったとも聞く。県には、そのような生産者の想いも踏まえて、このおいしい果実を消費者に届けてほしい。
一方で、紅プリンセスは、新品種であるため、まだまだ栽培方法が手探りな面もあり、生産者は試行錯誤を繰り返しながら高品質な果実の生産に向き合っていると聞く。また、近年の気候変動に伴う高温による生育への影響や、越冬栽培するため、今月上旬のような積雪があった場合には品質低下等の被害リスクが生じるなど、生産拡大していく上での課題は多く、生産者やJA等とも連携し、試験研究機関や普及機関も一丸となって、一つひとつ課題を解決しながら、早期に高品質で安定生産が可能な技術を確立してほしい。
7 本県の公共土木施設において、国の5か年加速化対策等の活用による成果はどうか。また、今後の防災・減災対策にどう取り組んでいくのか。
本県に甚大な被害をもたらした西日本豪雨から今年で7年が経過する。西日本豪雨が発生した平成30年度に、国は、防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策を創設し、この対策に続き、令和3年度からは5か年加速化対策として国土強靭化の取組みが加速化・深化しており、本県でも、公共土木施設における各分野での防災・減災対策が進んでいる。
また、加速化対策終了後の国土強靭化の継続については、5年の国土強靭化基本法改正で、国土強靭化実施中期計画の策定が法定化されたことから、県議会でも、昨年7月に防災・減災、国土強靭化対策の更なる推進を求める意見書を提出し、実施中期計画の速やかな策定等について要望した。
近年、全国各地で相次ぐ集中豪雨による被害に加え、先月には、南海トラ
フ地震の30年以内の発生確率が80%に引き上げられる等、大規模災害への備えは喫緊の課題であり、今後の国土強靭化の動向に注目が集まっている。
このような中、今国会での石破総理の施政方針演説では、8年度からの実施中期計画について、事業規模で加速化対策のおおむね15兆円程度を上回る水準が適切との考えに立ち、本年6月を目途に策定する方針が示された。
8 県教育委員会では、国際的に活躍できるグローバル人材の育成にどう取り組んでいくのか。
グローバル化が進展し、経済や社会、文化等のあらゆる分野で国境を越えた協力や調整等が必要となる中、これから社会で活躍する子どもが、言葉の壁を感じることなく、伸び伸びと自らの力を発揮するためには、実践的な英語力と併せ国際的な視野を身に付けることが重要である。
そのためには、義務教育段階から、実際の場面を想定したスピーキングやリスニングなどの練習機会を増やし、英語の実用的なコミュニケーション能力を強化することはもとより、海外の多様な文化に触れる機会を設けることで、広い視野とともに、異文化に対する理解や、異なる文化を持つ人と共に協調して生きていく態度などを育成する取組みが必要である。
県立学校振興計画では、今治西高校、松山西中等教育学校、宇和島南高校に国際関係の学科等を設置することとなっており、現在、各校の準備委員会において、学校のコンセプトや教育課程の編成等について具体的な検討が進められている。これらの学校では、語学力や国際感覚、実践的なコミュニケ ーション能力等を持つ人材の育成を目標としていると聞いており、先進的な国際教育によって、世界に通用する資質や能力を備えた人材が輩出され、我が国の国際競争力やイノベーションの向上に貢献することを期待する。
同時に、これら3校の取組みを県立学校全体に波及させるとともに、学校内にとどまらない、体験的かつ高度な学びを通して語学力や国際性を高めた若者が、県内企業で就職し、地域の持続的な発展に貢献できるグローバル人材となることが、今後、更に重要になってくると考える。
9 今治病院の移転新築の方針を含め、今後の県立病院の運営について、どう取り組んでいくのか。
昨年度の県立病院事業の決算は、新型コロナウイルスをきっかけとして減少した患者数がいまだ回復しない中、物価高騰や賃金上昇に加え、新型コロナの5類移行に伴い国の財政支援が大幅に減少したことにより、4病院全てが赤字に陥り、近年では最大規模となる33億円の赤字決算となった。
先般、昨年の医療機関の倒産件数が過去最多を更新したとの報道があったが、全国で多くの医療機関が、物価高騰の影響に伴う医薬品等の費用の増や賃上げに伴う人件費の増などにより、苦境に立たされており、本県の県立病院の経営を取り巻く環境も、依然として厳しい状況にある。
県立病院では、医師・看護師を始め人材が不足している厳しい状況にありながらも、とりわけ救急や周産期の現場では、その役割を全うすべく日々奮闘している。県は、こうした現場の頑張りに報いるため、12月補正予算において、約30年ぶりの高水準となる人事委員会勧告に基づく給与の増額改定を実施するとともに、今回の2月補正予算案には、厳しい経営環境に置かれている現状を踏まえ、給与改定差額緊急支援金として、給与改定相当分に対し、一般会計から支援を行う経費を盛り込んでいる。
一方で、来年度の病院事業会計当初予算案を見ると、人件費の上昇に加え、薬剤費や診療材料費等の高騰の影響を受け、支出額が収入を34.3億円上回る赤字予算となっている。看護師等の人材不足もあいまって、劇的な収支改善が見込めないことは十分理解できるものであり、赤字予算とは言え、県民の命と健康を守るために必要な経費はしっかりと確保し、医療提供体制が後退することのないよう、地域の中核病院として使命を果たしてほしい。
また、赤字予算を編成せざるを得ない厳しい状況の中、県民待望の今治病院の移転新築に係る予算も見送らざるを得なかったとのことであり、全国的に見ても、建設資材や労務費の高騰などの影響で、新たな公立病院の整備事業の見直しや入札不調が相次いでおり、本県でも、四国中央市で準備が進められていた新たな中核病院の整備事業が、医師不足や経営の悪化で一時中断していることなどを踏まえると、苦渋の決断であったことは想像に難くない。
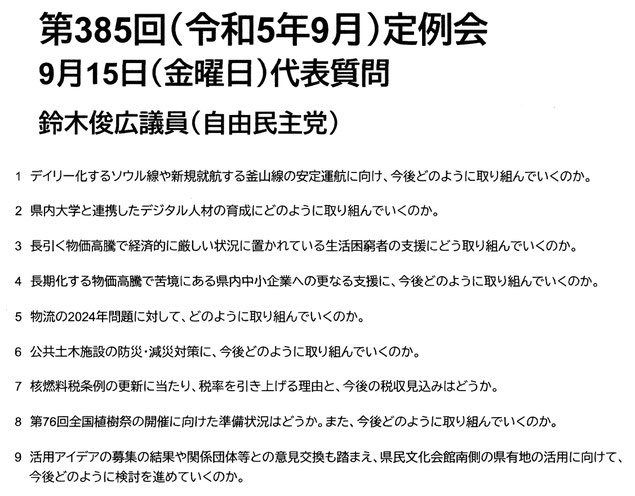
令和5年9月15日(金)No.1 代表質問 鈴木議員(自民)
1・デイリー化するソウル線や新規就航する釜山線の安定運航に向け、今後どのように取り組んでいくのか。
昨年10月、政府は水際対策を大幅に緩和し、2025年までに訪日外国人旅行者数をコロナ禍前の2019年並みに回復させるとの目標を掲げた。
それ以降、インバウンドは急速に回復しており、国の発表によると、訪日外国人旅行者数は本年の上半期で既に1,000万人を超えており、中国市場の動向次第で年間2,000万人を上回る可能性もあると言われている。
県内でも、松山城や道後地区などを中心に外国人観光客を見ない日はなく、コロナ禍前のにぎわいを取り戻しつつある。県内の観光事業者からも、本年3月末のソウル線の運航再開後、韓国からの旅行者が大幅に増加し、需要回復に貢献しているとの声も聞く。加えて、ソウル線の利用者はリピーターも多く、愛媛ファンが着実に増加していることから、今後も韓国から多くの人が来県することを期待している。
このような中、先月末、ソウル線が本年10月末から増便されてデイリー化するとの発表があったことに加え、一昨日には、本年11月から、釜山線が新たに開設され、週3便で運航されるとのうれしい発表もあった。
コロナ後、全国的に課題となっているグランドハンドリング人材の不足など、受入側の問題も乗り越え、松山空港の国際線で初めてデイリー化が実現したことや、釜山との新たな定期路線が開設されることは、知事を始め関係者が一丸となって困難を乗り越えてきたたまものであり、敬意を表したい。
引き続き、県においては、訪日外国人旅行者が大幅に増加している好機を逃すことなく、インバウンド需要の更なる取り込みを図るとともに、アウトバウンド利用者の拡大に向け、航空会社や旅行会社など関係機関との連携を一層強化し、ソウル線や釜山線の安定運航にしっかりと取り組んでほしい。
2・県内大学と連携したデジタル人材の育成にどのように取り組んでいくのか。
近年、急速に普及する生成AIを始めとするデータ活用やデジタル技術の進化により、世界規模で産業構造の変化が起こりつつある。最新技術はあらゆる産業のDXを加速させ、社会課題の解決に貢献することが期待されているが、それらを活用するのは人であり、DX推進の担い手となる人材の重要性が増すとともに、求められるスキルは多様化している。新技術の活用や普及、産業構造の変化に対応し、地域経済の活性化につなげるためには、産業、教育、行政等のあらゆる分野におけるデジタル人材の育成が急務である。
国によると、デジタル人材は2030年に最大で約79万人不足すると試算されている。このような中、文部科学省では、大学等におけるデジタル・グリーン等、成長分野への転換や学部設置・拡充等の促進を目的とした助成事業を公募し、本県では、愛媛大学と松山大学が採択されるなど、全国的にデジタル人材育成の動きが強まっている。
県では、デジタル人材育成の重要性にいち早く着目し、昨年2月に策定した「あたらしい愛媛の未来を切り拓くDX実行プラン」で、2030年度までにデジタル人材を1万人輩出という目標を掲げ、各種施策に戦略的に取り組んでいるほか、昨年12月には、県内の四つの大学と「愛媛県デジタル人材の育成・確保に向けた連携・協力に関する覚書」を締結し、国に先駆けて情報学部・学科等の新設に向けた取組みを進めており、頼もしく感じている。
昨年4月から、高等学校において新学習指導要領が実施され、情報Iが必修科目となった。情報Iを学んだ高校生が卒業を迎える令和6年度が一つの分水嶺となることを踏まえると、県と県内大学との連携による取組みは時宜を得たものであり、今後は、更にその先を見据え、輩出されたデジタル人材が県内に定着し、活躍できる環境を提供していくことも必要である。
3・長引く物価高騰で経済的に厳しい状況に置かれている生活困窮者の支援にどう取り組んでいくのか。
ロシアによるウクライナ侵略や、欧米各国との金利差に起因した急速な円安等により、我が国ではエネルギー価格や物価の高騰が長期間に及んでおり、我々の生活にも影響を与えている。日本銀行が本年6月に実施した調査によると、95%以上の人が物価上昇を実感していると回答している。
中でも、食料品は最も身近に物価上昇を感じるものであり、消費者物価指数によると、本年7月には、2020年を100とした場合に、食品全般が113.1となるなど、食品の物価が依然として高い状況にある。
このような物価高騰の長期化に対し、政府は、昨年4月に「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を、同年10月には「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を取りまとめ、その都度、補正予算を成立させるなど、国民の暮らし、雇用、産業を守るための施策を実行してきたが、食品など生活必需品の物価上昇に歯止めが掛からない状況の中で、特に低所得の人は大変な苦境に陥っていると推察する。
こうした人の生活を支えるため、市町では、国の制度に基づき、住民税非課税世帯に対して、昨年度は5万円、今年度も3万円の給付金を支給している。また、コロナ禍で収入が減少した世帯を対象に実施した生活福祉資金の特例貸付について、住民税非課税世帯は償還が免除されている。
しかし、住民税非課税となっていない低所得世帯は、市町の給付金や特例貸付の償還免除の対象外となっており、物価高騰の中にあって、ぎりぎりの状態で頑張っているのが実態ではないかと思う。
コロナ禍や物価高騰の影響で厳しい生活を強いられている人を支えるとともに、安定した就労や収入を得ることで生活再建につなげていくためには、一人ひとりの状況に応じた丁寧な支援が必要である。
4・長期化する物価高騰で苦境にある県内中小企業への更なる支援に、今後どのように取り組んでいくのか。
エネルギー・原材料価格や円安による輸入物価の上昇は、資源の多くを国外に頼る我が国にとって更なるコストの増加を招いている。
各企業では事業を継続していくため、業務体制の見直しや省エネの推進等のコスト削減に取り組んでいるが、それにも限界があるため、大企業を中心に販売価格や内容量等の見直しなど、消費者へのコスト転嫁が行われている。
しかし、本県企業の大半を占める中小企業では、取引先や消費者からの理解が得られない等の理由から、コスト転嫁が不十分な企業も多いと思う。
また、8月10日に開催された愛媛地方最低賃金審議会で、県内の最低賃金を現在の時給額853円から過去最大の引上げ幅となる5.16%、44円引き上げて897円に改正することが適当である旨の答申が出され、来月から改正後の最低賃金が適用されるほか、コロナ禍で行われた実質無利子・無担保の「ゼロ・ゼロ融資」の返済本格化など、今後、企業のコストは更に増加することが懸念される。
県では、特別高圧電気やLPガスへの支援を始め、省エネ設備の更新支援など、物価高騰の影響を受けている県民や事業者に寄り添った支援に取り組んでいるが、県内事業者を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、更なる支援が必要である。
5・物流の2024年問題に対して、どのように取り組んでいくのか。
平成30年に成立した働き方改革関連法が来年4月からトラックドライバーにも適用されることとなり、時間外労働時間が年間960時間までに制限されること等により、トラックによる輸送能力が不足し、これまでのように物が運べなくなる、いわゆる「物流の2024年問題」が懸念されている。
この問題に対して対策を行わなかった場合、営業用トラックの輸送能力が来年度には約14%不足、さらに、令和12年度には約34%不足する可能性があると試算されており、日時を指定した納入や出荷が難しくなるほか、配送時間が長くなるといった問題が生じ、荷主側の生産効率の低下や売上の減少、顧客の流出につながることが危惧されている。
本県は、柑橘や水産品などの生産量が全国トップクラスであり、首都圏など大規模な消費地への出荷のほとんどを長距離トラックによる輸送に頼っている。今後、出荷したい時期に出荷したい量を運べなくなれば、鮮度や出荷量において、産地間競争で不利になることも懸念され、生産者を始めとする荷主側にとって、輸送力の維持・確保は喫緊の課題である。
一方、トラック運送業界は、燃油価格の高騰などによる厳しい経営状況に加え、他の産業と比べて労働時間が長く、慢性的な人手不足に苦しんでおり、労働環境の改善や生産性の向上は重要な課題であるが、これは運送業界の自助努力のみで解決できる状況ではない。荷主側の企業や消費者の行動変容により、取引環境が改善されなければ、トラック事業者が十分なドライバーを確保し、輸送を更に効率化し、また、物流を維持していくことは困難である。
物流の2024年問題は、トラック事業者だけで対応できるものではなく、県主導の下、荷主企業を始めとする各業界の連携を促し、オール愛媛体制で取り組んでいくことが必要と考える。
6・公共土木施設の防災・減災対策に、今後どのように取り組んでいくのか。
南予を中心に甚大な被害が発生した西日本豪雨から5年が経過したが、県では、早期復旧に総力を挙げて取り組むとともに、肱川の堤防整備や砂防施設の整備のほか、地域からの要望の強い河床掘削の集中的な実施や緊急輸送道路の整備等の防災・減災対策を推進しており、心強く感じている。
その一方で、今年も全国各地で豪雨による被害が発生している。7月には、福岡県、大分県、秋田県などで梅雨前線豪雨による被害が発生しており、本県でも、6月30日から7月1日の2日間で松山市では平年の7月1か月分の雨量を上回る264mmの雨量が観測されるなど、全国各地で短時間強雨の発生頻度が高まっており、豪雨災害の激甚化・頻発化や自然災害がもたらす脅威を改めて実感している。
水害及び土砂災害のリスク増大に加え、切迫する南海トラフ地震に対する取組みが急務であり、いつ発生するか分からない大規模な自然災害から県民の安全・安心を確保することが、喫緊の課題となっている。
また、災害リスクが増大する状況下でも、地域経済の活性化や地域間交流の促進等、本県が更なる発展を遂げるには、その基盤となる強靭な県土の形成が必要不可欠である。
今後も、西日本豪雨を始めとした過去の被災経験の教訓を生かした、計画的な河川改修、津波・高潮対策、土砂災害対策、災害発生時に救援・救護の動脈となる広域道路網の整備、適時適切な避難行動の促進等、災害に強い県土を目指した不断の取組みを推進することが重要である。
7・核燃料税条例の更新に当たり、税率を引き上げる理由と、今後の税収見込みはどうか。
ロシアによるウクライナ侵略は、世界のエネルギー情勢を一変させた。我が国でも電力需給のひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じており、エネルギーの安定供給体制を強化する必要性が高まっている。
国内外の情勢が急変する中、一昨年10月には第6次エネルギー基本計画が、本年2月にはGX実現に向けた基本方針が閣議決定され、その中で、発電時に温室効果ガスを排出せず、熱効率にも優れた原子力発電は、安全性の確保を大前提に、引き続き重要なベースロード電源と位置付けられている。
一方、福島第一原発事故から12年が経過したが、原子力への社会的な信頼は十分に獲得されていない。原子力発電の安全性確保に関する第一義的な責任は発電事業者にあり、常に緊張感を持って安全性を追求する必要があると思う。このような中、伊方発電所では、一昨年7月に重大事故等対応要員である当時の社員の無断外出事案が発覚したほか、本年5月には定期検査中にトラブルが発生し、定期検査の工程が遅れるなど安全を脅かす事案が相次いでおり、原発立地地域の安全・安心の観点が置き去りにされているのではないかと危惧している。原発立地地域の声に耳を傾け、伊方原発の立地に伴う安全対策や地元の不安解消を最優先とした対応を切に願う。
本県では、昭和54年に核燃料税を創設して以来、安定的な税収を確保し、防災対策等の財政需要への対応を図ってきたが、今後も県民の安全・安心を確保するためには、伊方原発の立地に伴う安全・防災対策を着実に進めていくことが重要である。そのためには、来年1月が適用期限となっている核燃料税条例の更新は必要であり、原子力防災対策等をより充実させるためには、事業者である四国電力に応分の負担を求めることはやむを得ない。
8・第76回全国植樹祭の開催に向けた準備状況はどうか。また、今後どのように取り組んでいくのか。
先月、令和8年に開催される第76回全国植樹祭の開催県が本県に決定されたとの報道があった。森林が県土面積の約7割を占め、全国有数の林業県である本県での開催は、林業・木材産業関係者を勇気づけるものであり、中山間地域の振興を一層進めていく原動力にもなると考える。
去る6月4日、4年ぶりに天皇・皇后両陛下が御臨席される中、岩手県陸前高田市で第73回全国植樹祭が開催された。両陛下によるお手植え・お手播きなどの式典行事のほか、郷土芸能の披露や東日本大震災からの復興などをテーマとしたアトラクションにより、森林や木材利用への意識醸成や、震災復興への感謝と今後の思いを世界に向けて発信する感動的な大会であった。
本県では、昨年8月の開催内定以降、準備委員会による開催準備に着手し、先月には知事自らが会長として参画した実行委員会も開催されるなど、大会に向けた様々な検討がなされていくと聞いており、知事のリーダーシップの下、開催準備が着実に進んでいることを心強く感じている。
県内のスギ・ヒノキなどの森林資源は充実し、今後は、これらの豊富な森林資源を無駄なく利用し、再び育てるといった循環利用を進める新しい時代を迎えている。このタイミングで全国植樹祭が本県で開催できることは、我々一人ひとりが森林整備や木材利用に対する理解を深め、社会共有の財産である森林を守り、育て、支えていくための絶好の機会になるもので、多くの県民の参加を得ながら、開催機運が盛り上がることを期待する。
9・活用アイデアの募集の結果や関係団体等との意見交換も踏まえ、県民文化会館南側の県有地の活用に向けて、今後どのように検討を進めていくのか。
令和元年に県内で初めて開催されたG20愛媛・松山労働雇用大臣会合では、10億円以上の経済効果をもたらすなど、大規模な国際会議の開催は本県の国際的な地位の向上に寄与することを強く感じた。
本県は、人口や経済規模を見ると、四国でも中心となる地域であると自負しているが、拠点性の向上につながるコンベンション機能という観点では、国の出先機関が集積し、新香川県立体育館など、人の流れを生み出す施設の整備が進む香川県が一歩先を行っているようにも感じる。
また、長崎市では、市民交流を促進する拠点としてJR長崎駅前に大型コンベンション施設がオープンされるなど、他県の県庁所在地では、コンベンション施設を核としたまちづくりが積極的に進められている。
このような中、県では、駐車場として使用している県民文化会館南側の県有地について、先の6月定例県議会において、知事が活用方策の検討を開始、加速することを表明した。早速、7~8月にかけて県内外から活用アイデアを募集し、個人、法人から170件を超える応募があったとのことであり、改めて注目度の高さを認識した。
現在、県内には、他県と比較して、国内外から人や情報を呼び込むことができるMICE機能を備えたコンベンション施設が不足していると感じている。今回の県有地の活用に当たっては、他県に負けないコンベンション施設の整備も検討をし、本県の瀬戸内エリアでの拠点性の向上につなげてほしい。
また、これを契機に新たな人の流れが生み出されることで、本県の国際的な地位の向上につながり、国際航空路線の拡充やインバウンド観光客の増加、県内企業の海外での営業促進等に波及することも期待する。

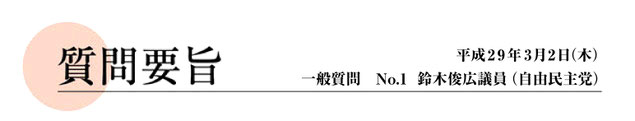
1 今治市への大学獣医学部の新設について、これまでどのように取り組み、今後 どのような姿勢で臨むのか。
獣医学部 ・学科がある大学は全国に16校あり、 そのうち 西日本には5校のみで四国にはない状況の中、業界団体や既存大学等の抵抗が根強く、昭和41年以降全国で新設が認 められてこなかったが、来年4月、今治市に開設されることが決定した。
今治市は、広島県と共に、国際教育拠点の整備を始め、観光・教育・創業など多くの分野でのイノベーションの創出を図るため、昨年1月、四国で初となる国家戦略特別区域に指定された。その後、内閣府や県の助言を得ながら、関係者が一丸となって、粘り強く規制緩和への道を切り開いてきた。
今回の大学獣医学部の誕生により、今治市に多くの若者が集まり、活気が生まれ、街ににぎわいが戻ることだけでなく、産業動物診療など公共の現場で不足する獣医師の安定確保やレベルアップの面で、県内全域、ひいては四国全域にもメリットが及ぶと考える。また、新しい獣医学部のコンセプトの下、多くの獣医師の卵が愛媛・今治で学び、鳥インフルエンザや口蹄疫など国境を越える家畜伝染病や人獣共通感染症対策に対応できる国際的な視野を持った公務員獣医師や創薬等のライフサイエンス分野の研究者などとして活躍することを期待する。
特に、人口減少問題を抱える本県では、多くの地元高校生が進学を機に県外へ転出し、卒業後も地元に戻ってこないという厳しい現実に直面する中、地元の志高い高校生がこの獣医学部に進学し、卒業後も引き続き地元で獣医師として活躍できる環境が整えられることは、この上ない喜びであり、開設に向けて全力で応援したい。
4月の大学獣医学部の開学に向けて、今治市を中心に鋭意様々な取組みが進められていると聞く。
2 東予東部圏域振興イベントの実施に向けた方向性と、今後のスケジュールはどうか。
四国中央市、新居浜市及び西条市からなる東予東部圏域は、製造品出荷額2兆円余りで本県全体の5割以上を産出する四国随一のものづくり産業の集積地である。地域ごとに見ると、法皇山脈が育んだ銅山川に建設されたダムの恩恵により、伊予の紙どころとして発展した日本一の紙の産地である四国中央市、住友グループ発祥の地で、中小機械産業群の層の厚い新居浜市、豊富な水資源を生かした食品産業や電気・電子産業、世界最先端の素材産業などを擁する西条市といった特色があり、自然と歴史に根差した多彩な産業が、愛媛はもとより、日本の経済成長を支えてきたと言っても過言ではない。
しかし、少子高齢化の進行は東予東部圏域にも暗い影を落とし、産業の担い手不足は深刻な状況にある。優秀な技能を持った技術者の引退が相次ぐ一方、進学や就職を機に若者の県外流出が続いており、足元の人手不足感はもとより、地域産業の発展の中核となる人材をどう確保するかが重要かつ喫緊の課題となっている。このため、県では、東予東部圏域を始めとした企業の魅力や技術力を県内外の若者に認識してもらうため、ものづくり企業の職場見学会や中高生向けのスゴ技企業紹介冊子の作成、合同会社説明会の開催など、人材確保に向けた様々な取組みを精力的に展開している。
こうした企業の魅力発信と併せて、「ここで暮らしたい」と思われるように、地域そのものの魅力を発信し、地域のブランドカを高めていくことも重要である。この地域は、西日本最高峰の石鎚山を始め、赤石山系、赤星山や翠波峰など魅力的な山が連なる法皇山脈等の豊かな自然に恵まれており、食についても、シャコやワタリガニ等の海の幸、四国中央市の新宮茶や里芋、西条市の野菜・果物などの山の幸、豊かな水を生かした地酒等の優れた素材がある。近年では、マイントピア別子を始めとする観光産業も拡充されつつある。今こそ、東予東部圏域に眠る地域資源を掘り起こし、磨き上げ、その多彩な魅力を県内外に発信し、住んでも訪れても魅力のある街として認知度を高めていく必要がある。
こうした中、県は東予東部圏域の3市長から同圏域振興イベ ント開催の強い要望を受け、地元と連携して平成31年度の開催に向けて動き出したことを心強く感じる。
大型の広域イベントが地域活性化の起爆剤となることは、瀬戸内しまのわ2014や、えひめいやしの南予博2016の成果を見ると明らかであり、東予東部圏域のイベントも地域の発展に寄与することを期待する。
3 企業の誘致及び留置対策に、今後どのように取り組むのか。
あるシンクタンクによると、日本経済は米国トランプ政権に関する不透明感の高まりによる不安要素があるものの、緩やかに回復しており、今後も引き続き同様の傾向が続くと予想されている。自民党の政権復帰以降、安倍総理が長引くデフレや内需縮小などの難題に対して、いわゆる「三本の矢」と、それに続く「新三本の矢」を掲げて矢継ぎ早に景気対策を実施し、日本経済の再生に取り組んだ結果、2倍を超える株価の上昇や過去最高水準の企業業績につながるなど、着実に成果を上げている。
このような中、国内における企業の設備投資は増加しており、中小企業が多い本県でも同様の傾向が見られている。県内調査会社の調査では、今年度、本県立地企業が県内で行う投資総額は昨年度を上回り、特に製造業では約6割の企業が何らかの設備投資を行う見込みであり、この状況は本県で新たな雇用を生み出す絶好の機会となるほか、地方創生の流れにもつながるものと心強く思う。
一方、超少子高齢化社会を迎える中、地方では人口減少に伴う地域経済の衰退に危機感を持っており、地域経済の発展と人口減少対策の一つの手段として企業誘致を強力に進めている。今後、地方間での誘致競争はますます激しくなり、特に、県内立地企業が県外へ流出する危険性もあることに不安を感じる。
本県が将来にわたり生活水準や人口を維持するためには、若者が働きたいと思える企業の誘致に加え、県内立地企業が県外へ流出しないよう、優秀な人材の確保を始め、新たな投資及び拠点化の取組みに対する支援や事業用地の確保など、留置対策を講じる必要がある。
4 女性活躍の推進も含め、ひめボス推進キャンペーンをどのように展開していくのか。
安倍総理は今国会の施政方針演説で、一億総活躍の国創りに向けた最大のチャレンジとして、一人ひとりの事情に応じた多様で柔軟な働き方を可能とする働き方改革を掲げた。また、女性の活躍について、出産などを機に離職した人の再就職等への支援を抜本的に拡充するとともに、成長と分配の好循環を創るため保育や介護と仕事の両立を図ると明言した。
この働き方改革の目的は、人口減少・少子高齢化社会において、労働力人口が減少し、働き手が多様化する中で、誰もが能力を最大限に発揮できる環境を整備するとともに、企業の生産性を高め、地域の活力向上につなげることであると認識 している。働き方改革のトップランナーである本県出身のIT関連企業社長は、働き方改革には制度、ツール、風土の三つの要素が必要であると述べている。重要なのは職場風土づくりであり、企業や団体のトップの強い意思表示が第一に求められている。
今年1月、知事は、「職員の仕事と家庭生活、地域活動などの両立を支援しながら、組織としての成果も出し、自らも仕事と私生活をまるごと楽しむ愛媛のイクボス『ひめボス』となり、さらにその取組みを県内企業や団体等にも広げて、愛媛の活性化を目指す」という「ひめボス」宣言をした。また、先月15日には県と市町が合同で宣言を行い、県内自治体が連携して発信することで「ひめボス」宣言を県内事業所へ波及させるひめボス推進キャンペーンを展開していると聞く。
本県では、企業の99%以上を中小企業が占めているが、トップの判断で職場環境を変えることができるという中小企業ならではの利点を生かし、トップが率先して新しい働き方を実践することで社会を変えてほしい。
また、中小企業等では慢性的な人材不足となっている一方、女性の労働力率は結婚や出産を機に離職するいわゆるM字カーブが解消されておらず、女性が働き続けることができる環境づくりや長時間労働の見直しなどの働き方改革は、人材確保の観点から企業の経営戦略にもなり得ると思う。
昨年4月、従業員301人以上の企業に対して女性活躍の事業主行動計画の策定公表を義務付ける、いわゆる女性活躍推進法が施行され、大企業を中心に女性活躍の取組みが進みつつあるが、中小企業等でも女性活躍と働き方改革を複合的に推進することにより、地域人材の確保や経済の活性化にもつながると考える。
5 土木分野におけるドローンの活用にどのように取り組むのか。また、操縦技術の向上など、安全かつ効果的な活用に向けた取組みはどうか。
平成27年12月に施行された改正航空法で無人航空機であるドロー ンの定義や飛行ルールが定められ、ドローンの利用が拡大している。例えば、電力会社における設備点検やケーブル敷設、警備会社における不審者の発見等の防犯対策など、様々なビジネスでドローンが活用されている。
また、本県でも国家戦略特別区域の指定を受けた今治市で、昨年10月に離島での物資輸送を想定したドローンによる荷物の宅配実証実験が行われ、高齢化が進む島しょ部住民を支援する取組みの実用化に向けて、現在も実験
が続けられている。
特に、土木分野においては、既に大規模災害時等の調査でドローンが有効活用されている。昨年10月に国土地理院を視察し、ドローン等の最新技術を活用した防災対策の推進状況を調査した。27年9月の関東・東北豪雨では、鬼怒川の堤防が決壊し甚大な被害が発生したが、同院では鬼怒川に職員を派遣し、決壊から僅か4時間後にドロー ンを飛行させて決壊箇所やいっ水の状況を撮影するなど被災状況の把握や応急活動に必要な情報を収集し、関係機関に速やかに提供することで早期の復旧につながった。また、熊本地震でも調査が困難な危険箇所等で、ドローンを活用して被災状況を迅速かつ安全に把握し、応急対策の立案に活用するなど、災害現場での有効性が確認されたところである。
このようにコンパクトでありながら様々な可能性を秘めたドローンは、今後、災害現場だけでなく、公共測量での利用や施工での活用など、ますます活躍の場が広がると考える。
6 ストーカーやDV等の人身安全関連事案に対して、どのような方針で取り組んでいるのか。また、今後の取組みはどうか。
人身安全関連事案は、生命・身体への危害はもとより、社会生活の安全・安心を脅かす卑劣な犯罪であり、最近では、昨年5月に東京都で芸能活動をしていた女子大学生が、SNS等への書き込みを繰り返していた男に刃物で刺される事件が発生し、社会的な注目を集めた。
この種の事案は、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強い場合が多く、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあり、危険性の判断を迅速かつ的確に行い、犯人の早期検挙や迅速かつ継続的な被害者の保護活動を行う必要がある。
このような中、昨年12月にストーカー規制法が改正され、SNS等で連続してコメントを送る行為が新たに規制されたほか、県警では、平成27年度以降、順次警察官を増員してこの種の事案への即応体制の強化を図っていると聞く。体制の強化と的確な対応が県民の安全・安心の確保につながっていると考える。
県警には、県福祉総合支援センター等の関係機関・団体との連携にも配意し、今後も引き続き被害の未然防止と被害者保護対策にしつかりと取り組んでほしい。